こちらはエムスリー Advent Calendar 2024 7日目の記事です。 前日は大垣さんのアニメキャラらしさ姓名判断師AIを作る ~字画に注目したモデリング~でした。とても面白いのでそちらもどうぞご覧ください。
はじめに
こんにちは。AI・機械学習チームの氏家(@mowmow1259)です。
今回のテーマはリモートワークです。 最近オフィス回帰の流れがあるとはいえ、リモートワークを導入する企業はコロナ禍以前と比べて確実に増えてきています。 エムスリーでも2021年からリモート勤務がベースとなっており、さらに最近では関西と九州にもサテライトオフィスができるなど、全国各地からリモートワークで開発を進めています。
リモートワークは通勤時間がない、家事育児などプライベートな時間と仕事を両立しやすいといったメリットがある一方で、生産性を落としてしまったり、メンタルが不調になってしまったりなどの事例もよく耳にし、リモートでの仕事の難しさを感じています。 そんな環境の中、私が所属するAI・機械学習チームではリモートワークでも健全で効率的に仕事をするために試行錯誤を重ねてきました。 そこで今回は、弊チームで実践している、リモートワークでうまく仕事を進めるための取り組みを紹介したいと思います。

仕事の進め方編
リモートワークではテキストコミュニケーションが主体となるためコミュニケーションコストが大きくなり、出社時のように気軽に質問や相談をすることが難しくなります。 そのため、相談をしやすい環境を意識的に作っていくことが重要です。
ここでは、そのためにAI・機械学習チームで実践しているリモートワークでの仕事の進め方を紹介します。
Working Out Loud
リモートワークにおける仕事の進め方において最も重要だと感じているのはWorking Out Loudの文化です。
これは、その名の通り、仕事の内容、状況がチームメンバーに見えるように大声で作業しよう、というものです。 もちろん実際に大声を出しながら仕事をするわけではなく、Slackなどのチャットツールで実況しながら仕事をしています。 Working Out Loudの働き方についてはさまざまな記事で紹介されていますが、スタディサプリさんの記事がわかりやすいです。
弊チームではこの働き方が強く推奨されており、チームメンバーはもちろんインターンの方もこの文化に染まっていきます。 方法は何でもいいのですが、個人的には「〇〇をやるスレ」などスレッドを立てて、そこに作業や思考の過程などをそのまま垂れ流すことが多いです。
チームメンバーはスレッドを見かけると、その内容について自由にコメントしていきます。 アドバイスをすることもありますし、単に感想やスタンプを送ることもあります。 一見無用なコメントに見えても、何かしらの反応がもらえることは発信者の心理的な障壁を下げてくれます。
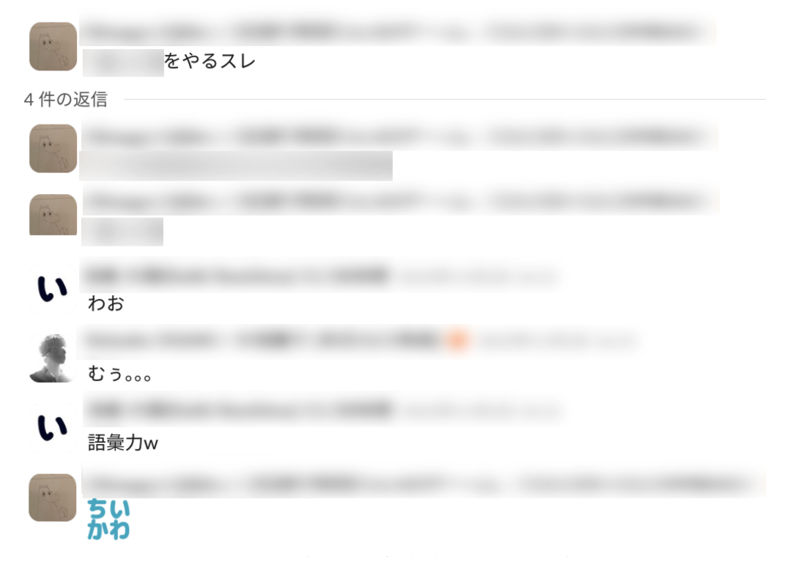
書き込む本人にとっては、相談のハードルが下がることが大きなメリットです。 リモートワークではオフィス出社時のように同僚に気軽に話しかけることが難しいため、相談のハードルが上がりがちです。 Working Out Loudをチームで実践していると、困り事は同僚との会話(スレッド)の中で自然に相談する流れになり、相談のハードルがかなり下がります。 むしろ、わざわざ相談のためにメンションせずとも、スレッドを見たチームメンバーが颯爽と問題を解決していくことも多々あります。
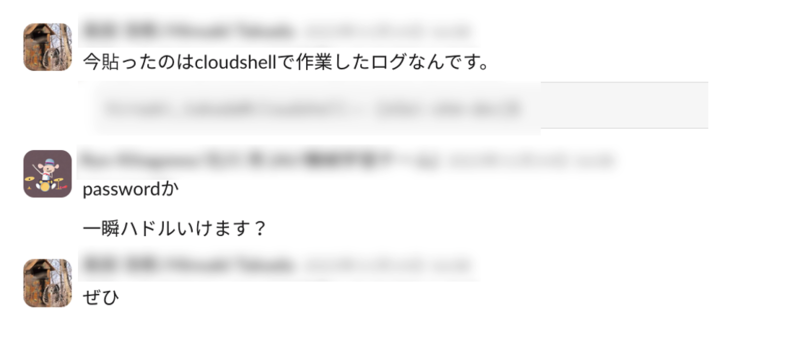
また、作業が逐次共有されることにより、間違った方向に進んでしまった際の軌道修正も早くなります。 朝会や定例を待っていると、問題が発覚した頃にはすでに結構な量の作業をこなしてしまっていた、なんてこともありますが、作業ログを逐一残していくことで、スレッドを覗いたメンバーが早期に指摘してくれる場合が多々あります。
同期コミュニケーションの活用
Working Out Loudによる非同期コミュニケーションを最初に紹介しましたが、とはいえ仕事を進める上では同期コミュニケーションも重要です。 弊チームではZoomやSlackのhuddleを利用した、主に4つの同期コミュニケーションのパターンがあります。
定期的な同期コミュニケーション
最も基本的な同期コミュニケーションの場として、弊チームでは仕事内容が近いグループで15-30分の朝会を実施しています。 これはリモートワークに限らず実施している企業が多いと思いますので多くは語りませんが、前日やったこと、その日やること、相談事項を同期で確認しており、仕事を進める上でのマイルストーンとして活用しています。
また、朝会はグループ分けされているため、他グループのメンバーが何をやっているかを把握することは難しくなってしまいます。 そこで、毎週末に15分ほど週例の場を作り、担当プロダクトの状況を共有する会としています。 チーム全体に向けて進捗共有することでプロダクト間で思わぬシナジーが生まれることもありますし、普段関わらないメンバーから新鮮なコメントをもらえることも多々あります。
突発的な同期コミュニケーション
前述のような定期的な同期コミュニケーションの他、突発的なZoomミーティングが起こることも多くあります。 リモートワークでは同期コミュニケーション自体にハードルがあるためテキストで済ませがちですが、テキストで意図が伝わりきらず、認識齟齬があるままプロジェクトが進み、後々致命的な問題が発覚することもあります。 また、どう考えても同期で話した方が話が早い場合もありますよね。 そのため、複雑な状況を伝えたり、コミュニケーションに違和感がある場合には「シュッと15分くらい話しませんか?」などと言って突発的にZoomミーティングを開くことも推奨しています。
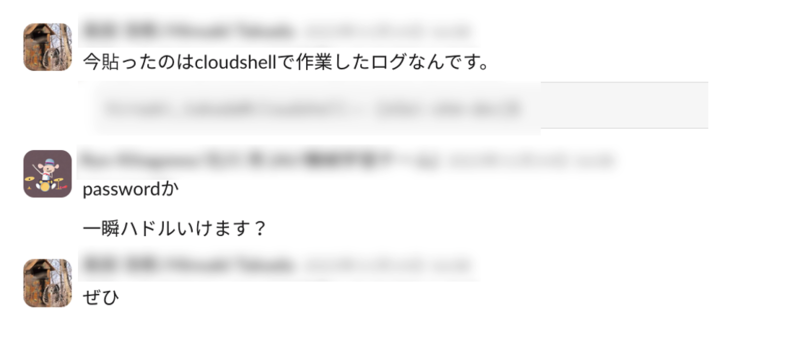
オンボーディングのためのデイリー1on1
リモートワークでは新メンバーのオンボーディングも難しいポイントです。 もちろんSlackでも歓迎ムード一色ですし、朝会やSlackで相談しやすい環境を作る努力をしていますが、とは言っても入社直後はわからないことだらけですし、テキストで気軽に相談する関係性も構築できていない場合もあり、相談できずに仕事が進まない、なんてことになりがちですよね。
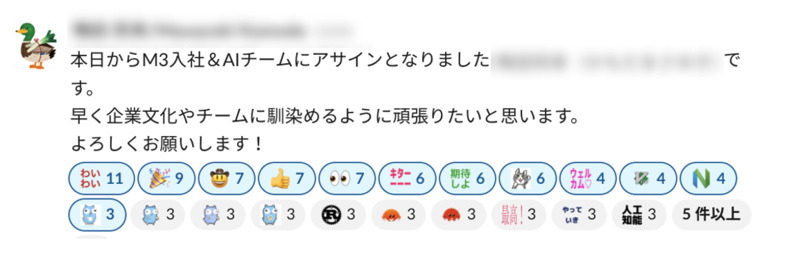
弊チームでは、新メンバーやインターンの方には一人一人にメンターがつき、1ヶ月間を目安としてデイリー1on1を実施しています。 毎日1on1をすることにより、業務の相談しやすくするのはもちろん、入社直後の不安や悩みの相談などをざっくばらんにできる場にもなっています。
互いを褒め合う文化
テキストコミュニケーションではやりとりが淡白になってしまい、ポジティブなフィードバックは意識的にしていかないとおざなりになりがちです。 AI・機械学習チームでは、#ai-fact-sheetというチャンネルを作り、同僚の良かったところを褒め合う文化があります。 元々は毎期末の360度評価のために始まった取り組みですが、今では同僚に感謝を伝える場としてもかかせないチャンネルですし、チームの良い文化がポジティブなフィードバックとして明示されることで文化醸成にも一役買っています。
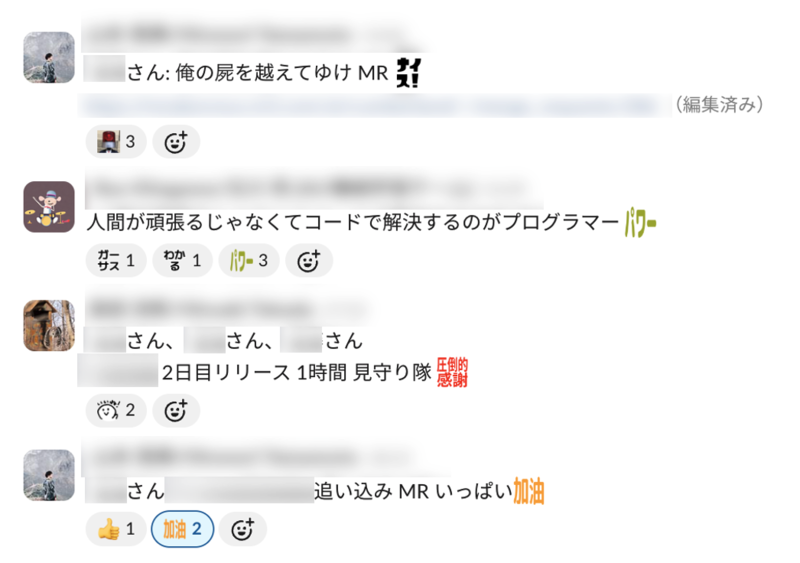
また、それとは別に、特に上司(弊グループではTL、GM)への感謝を伝える「TLの日」という取り組みも年に一度エンジニア組織全体で実施しています。 上司のサポートは当たり前に感じがちですが、上司だって人間です。 このような場を借りて上司にもポジティブなフィードバックをすることで、組織全体として働きやすい環境になっていると感じています。
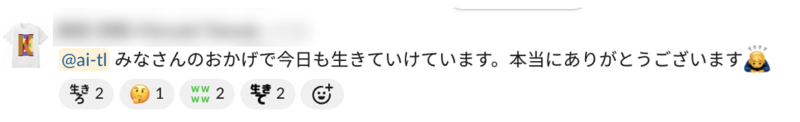
雑談コミュニケーション編
ここまで仕事の進め方を紹介してきましたが、ここからは雑談コミュニケーション編です。
リモートワークでは、出社していた時には自然と生まれていたオフィスやランチでのコミュニケーションが生まれず、チームメンバーの人となりがわかりづらくなっています。 雑談をはじめとしたコミュニケーションは、メンバーの人となりを理解し心理的安全性を上げるためにも、またメンタルケアの側面でも非常に重要です。
ここでは弊チームで実践している取り組みをいくつか紹介します。
1日1度の雑談夕会
夕方に10分程度Slackのhuddleに集まり雑談をする「雑談夕会」を開催しています。 その日話すお題を決め、一人一人そのお題に沿って話をしていきます。 お題は「最近注目している技術」といったエンジニアリングに関するものから「お気に入りの持ち物を語る」のような趣味全開のものまで多種多様です。
お題はあらかじめストックされたものから自動で決まるようになっています。 こちらの記事では、今日からお使いいただける雑談テーマを決めるスプレッドシートを紹介していますので是非ご覧ください。
この夕会は私が入社した3年前からずっと続いていますが、プロジェクトが違うメンバーともこの雑談では必ず話せるので、個人的に大切にしている場です。 社会人になってからプライベートで友人と雑談する機会がめっきり減ったこともあり、息抜きとしてもすごく助かっています。
times文化
times文化とは、「times-ujiie」のようなメンバーごとに作成されたチャンネルです。 これは実践されている企業も多いかと思います。 使い方は本当に自由で、自分のタスクを日報的にまとめている方もいますし、社内のXのようなイメージでとりとめのない雑談を垂れ流しているメンバーもいます。
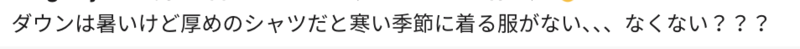
雑談を主目的にしているチャンネルのため、他チャンネルよりも発言のハードルが低く、当然ですが他メンバーと雑談が起きやすくなります。
ただ、雑談を活性化してくれるtimes文化ですが、上記記事でも言及されている通り井戸端会議の会場になってしまう可能性もあります。 個人的な運用としては、業務に関することは書かず、完全に雑談に振り切っています。 私も模索中なので、みなさんの意見も是非コメント等で教えていただけると嬉しいです。
オフラインコミュニケーション
ここまで長々とリモートワーク下でのコミュニケーションを語ってきましたが、そうは言っても、実際に会って交流するのも時には必要だと感じています。 リモートワークを経験してきて、やはりZoomやテキストによる会話は実際に会って話すのに比べて淡白になりがちだという実感があります。 私は入社当時からリモートワークでしたが、入社後しばらくしてから初めて実際にお会いしたチームメンバーに「氏家さんってこんなに声に出して笑う方だったんですね」と言われたことがとても印象に残っています。
そのため、AI・機械学習チームでは年に3-4回程度はチームでオンサイトで集まる機会を設けています。 オンサイトで集まるからには盛り上がることをしよう、ということで、開発合宿やGameDayなどを開催している他、全社でのLT大会や懇親会、忘年会などの飲み会まで様々なオフラインイベントを企画しています。
まとめ
今回はAI・機械学習チームのリモートワークを支える文化についてご紹介しました。 リモートワークに焦点を当てて取り組みを紹介していきましたが、オフィスに出社している際にも有用なものも多くあります。 今回ご紹介したもののうち、チームに合いそうな取り組みを是非取り入れてみてください。
また、これ以外にもリモートワークでうまくいっている取り組みがあれば是非コメントでご紹介ください!
We are hiring !!
エムスリーでは東京だけでなく、関西と九州でもサテライトオフィスが開設され、大阪、京都、福岡でもエンジニアを募集しています。 リモートワークでゴリゴリと開発をしたい方は是非ご応募ください。